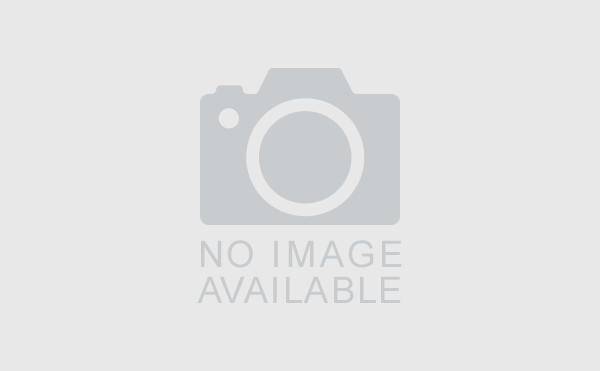【1年生の皆さんへ】ゼミ生の日常特別編~森先生の日常〜
今回は、「ゼミ生の日常特別編~森先生の日常〜」をお送りいたします!1年生の皆さんに森先生のお仕事の様子やお父さんとしての優しい一面などを見ていただきたく、森先生に記事を書いてもらいました!私たち森ゼミ現役生も気になっていた、森先生の日常、のぞいてみましょう!
〈大学教員・研究者としての森先生〉
森です。ゼミのリクルート係の皆さんより、日常やプライベートの事について書いた記事を投稿せよとの指示がありましたので、投稿します。
まず仕事の日常について。大学教員の日常的な活動は一般的に、<教育>、<研究>、<大学運営>という三本柱で構成されています。学生の皆さんとは、教育という活動を通じて接しているわけですが、普段みなさんから見えないところでは、研究とか大学運営というものにあたっています。この三つをバランスよくまんべんなくやるか、あるいは特定の活動に力を傾注するかは、その教員次第です。何か決まりがあるわけではありません。教育については、皆さんはなんとなくイメージを持っていると思いますので、<大学運営>と<研究>について少しだけ書いてみようと思います。
さて、<大学運営>というのは、一言で言って、授業やカリキュラムに関することから入試のこと、その他大学の諸制度に関する様々な事柄にまつわる事務を処理することです。事案によっては、学生さん個人に関することなどにも対応することもあります。教授会という会議も、だいたい隔週で月曜午後に開催され(月曜午後に法学部専門科目がないのはそのためです)、法学部の先生方が集まって様々なことについて審議します。また、大学内には、大学を運営するための数多くの委員会があって、各学部から委員の先生が出席して、大学全体の大きな方針や細かい事務に関して報告を受けたり、審議をして承認するという仕事があります。私は2019年度からボアソナード記念現代法研究所(ボアソナードタワーの22階にある研究所)の所長という役職にありますので、研究所の運営事務を職員の皆さんの助けを得ながら処理したり、研究所の運営委員会という委員会での報告や審議に向けた事務を処理したり、総長や大学内の研究所の所長さんたちが出席する研究所長会議という会議に出たりしています。
<研究>には、実に様々な活動が含まれますが、これも教員によって種類や分量は様々です。私の場合、論文や本の執筆から研究会(研究者が集まって専門的な研究テーマについて報告者が研究成果を発表して議論する場)や学会での発表、国内外で開かれる国際会議への出席や海外での講演、東京にいる外国の外交官からの意見交換の依頼やメディアの取材への対応、さらに政府関連の会合での報告や意見交換などが主な活動です。国会議員の先生に依頼されて、国会議員の先生方の集まりで専門分野のお話しをすることもあります。
多くの研究者にとって、論文を書いたり、研究プロジェクトで組織する研究会で自分が研究成果を報告したり、他の研究者の研究報告について討議しながら最新の知見を吸収したり、研究対象が外国の場合は現地に足を運んで、現地の人々から話を聞いたりして調査を実施することなどが研究活動の中核を成しています。専門分野の新刊の研究書や論文を読むのは言うまでもありません。また、私は中曽根平和研究所というシンクタンクで上席研究員というポストにあるので、研究所の研究会の運営にも係わっています。
論文の刊行本数は、年にもよりますが、論文集や学会誌に収録されるフルのものは年間2~3本、短いものはたくさん書いています。研究プロジェクトは、以下のようなものに加入しています。この原稿を書くために改めてリストアップしてみたら、19になっていました。これ以外に、ここには詳しく書けませんが、政府の研究プロジェクトを2件と研究会を1件やっています。新型肺炎の感染が拡大している上半期は、ほとんどストップしていましたが、夏頃から動き出して、スケジュール管理だけでもひいひい言っています。
- 科学研究費(日本学術振興会)・基盤(A)「先端技術と国際秩序:革新技術がもたらす国家のパワー、権威、倫理の変容」
- 科学研究費(日本学術振興会)・基盤(B)「米国による同盟の戦略的調整に関する比較歴史研究:脅威認識、安心供与、コスト分担」
- 中曽根平和研究所「コロナ後の世界秩序」研究会
- 中曽根平和研究所「米中関係」研究会
- 中曽根平和研究所「宇宙・サイバーと先端技術」研究会
- 中曽根平和研究所「米大統領選とこれからの北東アジア」研究会
- 中曽根平和研究所「防衛問題」研究会
- 日本国際問題研究所「大国間競争時代の日米同盟」研究会
- 日本国際問題研究所「アメリカ」研究会
- 日本国際問題研究所「安全保障と新興技術」研究会
- 笹川平和財団「アメリカ現状モニター」
- 日本国際フォーラム「チャイナリスクとチャイナオポチュニティ」研究会
- サントリー財団研究会
- 法政大学ボアソナード記念現代法研究所「現代国際秩序における正統性の相克」
- 政策研究大学院大学「インド太平洋戦略」研究会
- 東京大学「米中競争による先端技術の安全保障化の背景とグローバル経済への影響」
- 慶應義塾大学「ゲームチェンジャー技術と安全保障」
- 慶應義塾大学「朝鮮半島の構造変動」
- 富士山会合ヤングフォーラム「次世代の安全保障」研究会
授業をしながら、これらの活動を実施するのはなかなか大変で、一日36時間くらい欲しいと常々思っています。多忙な時期は、基本的に朝型で活動しています。朝4時に起床し、6時くらいまで翻訳作業などをしてから、7時過ぎに家を出て、大学の通用門が開く8時前後に研究室に入って仕事を始めます。現在は、授業日の火・水も含めて週3~5日くらいは研究室で仕事をします。研究会に出席したり、政府関係者や東京にいる外国の外交官と会食したりする日は、ちょっとずつ増えています(ネクタイを締めているのは、だいたい学外で仕事がある日です)。睡眠時間はなるべく6時間はとるようにしていますが、多忙な時は4時間という日も続きます。でも最近は歳のせいで無理もきかなくなってきました。
ということで、教室で授業をしている時間以外に、研究室でお茶をすすって、のんびり好きな読書をしているわけではありません(そうすることが夢ですが)。
また、夏休みや春休みの時期は、海外出張に出たり、原稿を集中的に書き進めたりしますので、あっという間に終わります。コロナ前は、海外出張が多く、外国の政府や研究機関から国際会議に招待されて講演に行ったり、政府から依頼を受けて講演に行ったり、自分の研究費で調査に行ったりしていました。ここ数年はだいたい毎年アメリカ(ワシントンとハワイ)、中国、韓国、東南アジア、中東、ヨーロッパに出張しています。昨年は、行った順番に書くと、ワシントンDC、ロンドン、ホノルル、クアラルンプール(マレーシア)、ワシントンDC、サンフランシスコ、北京、台北、ロンドン、キャンベラ・シドニー、ワシントンDCに出張しました。
【インドネシア大学ASEAN研究センターでのシンポジウムにて】

※この時は、自主海外調査旅行でジャカルタにいたゼミ生がジャカルタ郊外のインドネシア大学のデポックのキャンパスまで来て、この講演会の会場で傍聴していました。
仕事柄、世界中の情報が集まるワシントンDCに行くことが多いです。今年の2月末にワシントンDCに国際共同研究会で行った時には、まだ中国や韓国、日本で新型肺炎が拡大していたものの、アメリカの感染者数は1ケタでした。日本で売り切れになっていた消毒用ジェルを現地のドラッグストアで何個か買って帰りましたが、友人によると、その翌週から各地のドラッグストアから消毒ジェルが消えたそうです。その後は皆さんもよくご存知の通りです。
2018年には、欧米諸国以外に、テヘラン、アンマン、アルジェ、チュニス、カイロ、マドリッドなどの大学にも行って、日米中関係やインド太平洋戦略や一帯一路の話をしてきました。話が通じない相手と一生懸命議論するのは大変な時もありますが、反応が新鮮ですし、相手の見方に触れるのはとても楽しくて面白いです。これは外国出張の醍醐味ですね。
コロナ前の最後の出張は、3月上旬の南米ペルーのリマでした。ここで短く旅行記(出張記?)を書きます。リマまでは、アメリカのヒューストン経由で、乗り継ぎ時間も入れて24時間くらいかかりました。ヒューストン=リマ間のユナイテッド航空の便は、私を除いてほとんど誰もマスクをしていなくて、「オイオイ大丈夫かよ」と、さすがにちょっと心配になりました。ちなみに、このとき成田空港のANAスイートラウンジは、すでに感染防止対策を徹底して、飲み物は缶のものだけになり、コーヒーすらカップで飲めなくなっていて、缶コーヒーが出てきました。当時は「そこまでする?」と思いましたが、今から思えば大正解の対応だったと思います。
さて、ペルーは現在、中国と自由貿易協定(FTA)の交渉をしていて、現地の外務省で政府関係者の方々を相手に米中の技術覇権競争に関する講演をしましたが、質問が止まずに1時間ほどオーバーして、関心の高さを実感しました。ペルーはファーウェイを受け入れているのですが、「我々はリスクなど気にしません。アメリカのでっち上げもあるのではないですか」と言うので、「そうですか、そしたら中国とFTA交渉をする時の交渉団の控室で、ファーウェイの携帯電話やタブレットをどんどんお使いになられるのですね」と返したら、押し黙っていました。色々と聞いていくと、内心誰しもヤバそうだなと思いつつ、でも安いので使わざるを得ないからヤバいとは言えない、ということのようです。現地の国立サンマルコス大学(アメリカ大陸最古の大学で創立はなんと1551年!)でも講演をしましたが、そこでは学者や学生の皆さんと質疑応答をしました。アジアから遠く離れた南米でも皆さん、予想以上に米中関係に強い関心を寄せていて、自分たちのところにも色々と影響が波及してくるのではないかと心配していました(ペルーは中国と経済関係を結びつつ、対米関係もうまく保つ外交をしている)。米中関係は、もはや誰しもが目を向けるグローバルな国際政治問題になっているということを南米大陸で実感しました。
私が滞在中にペルーでも感染者が少し出始めましたが、ペルーは医療体制が十分に整っていないため、政府が早めに対応を判断して、私がペルーを出発した翌々日に国境を閉鎖しました。ぎりぎりセーフでした。日程があと2日ずれていたら、何カ月かペルーで足止めを喰らっていたと思います。行きはヒューストン空港のビジネスラウンジの食事が割と美味しかったので、帰りもちょっと楽しみにしていたのですが、ペルーに行っている間に、アメリカでも緊急事態宣言が出てしまい、帰りのヒューストンのラウンジの食事はすべて撤去され、ペットボトルの飲み物だけという状態になっていました。ヒューストン=成田のANA便は、ガラガラでCAさんも手持無沙汰みたいで、食事のときなどは、前菜が終わると、ささっと絶妙なタイミングで食事を下げてくれる、というような感じでした。(普段出張でANAには随分お世話になっていて、ゼミのOGも就職しているので、いま同社が大変な目に遭っているのが気の毒です。ANAは武漢から日本人を運ぶという大変なオペレーションも請け負ったので、救済措置を講じたりできないものなのかなと思います。なんとか会社の助けになれないものかなあと思う今日のこの頃です。)
とまあ、こういうあちこち飛び回る生活を何年もしていたので、最近では、オンラインで行われるようになった国際会議に招待されるようになりました。ところが、時差があって、たいてい朝一番か夜の時間帯になります。したがって、朝8時から10時まで国際会議に参加してから2限目の授業をやったり(アメリカ東海岸の夕方の会議など)、夕方に研究会を終えて帰宅してから21時半から23時半まで国際会議に参加したりすることもあり(ヨーロッパの昼の会議など)、なかなか大変な世の中になってきました。
【日米有識者による富士山会合にて】

つい先日は、バイデン陣営の中枢部に入るであろう友人の専門家たちとオンライン会合を持ちました。このオンライン会合では、ちょうど私が2013年から2015年にワシントンDCで在外研究していた時に、会議で出会い、対中戦略のあり方で意気投合した友人とも久しぶりに会い、会合後にもやり取りをしました。バイデンさんがオバマ政権の副大統領のときに、国家安全保障担当の次席補佐官を務めていた対中戦略の専門家で、ワシントンDCで滞在していた頃は、よく研究会に招いてもらい、帰国後も彼の所属するシンクタンクの会議などにも招いてもらいました。ワシントンに出向いた時には、ホワイトハウス脇のアイゼンハワー行政府ビルを訪ねて、会議室に通してもらい、南シナ海における中国の動静と今後の政策課題について意見交換をしました。そのときはアメリカ政府の開放性を肌身で実感したのを覚えています。バイデン陣営の専門家集団は、すでに政権入りする準備のために、千人以上の専門家たち(政権が発足したら政治任用者として一斉に政府要職に就く人々)が、同盟国の専門家たちの意見も聞きながら、政権発足後の世界戦略を練る準備をしているようです。
【アイゼンハワー行政府ビル】

【アイゼンハワー行政府ビル内の会議室】

【会議室内にて】

ところで、話は変わりますが、1年生の皆さんは、まだほとんど市ヶ谷キャンパスに足を運んでいないと思います。一つ言えることは、法政大学は九段下・神楽坂という素晴らしい台所を抱えていて、「食」からみると、その立地はこの上なく恵まれています。私が行きつけのお店は、例えば靖国通りにある「九段斑鳩」というラーメン屋や、同じ九段にある「とんかつ 針の山」です。前者は化学調味料なしのラーメンを提供する専門店で、大学院生の頃からお邪魔しています。素晴らしいラーメンを創って、多くの人々に幸福感を提供しているご主人をリスペクトしています。後者は、ソースに加え、4種類の塩でトンカツをいただける美味しいお店です。私はいつも「ヒマラヤ・ブラック」という黒っぽい、少し温泉の硫黄っぽい香りのする岩塩でいただいています。
神楽坂だと、たとえば海鮮丼の「つじ半」、「九頭龍蕎麦」(越前おろし蕎麦の大根おろしが辛くてうまい!)、中華の「芝蘭」(ごはん、ザーサイ、杏仁豆腐がおかわり自由)や「龍公亭」などに足を運びます。飯田橋の「ラーメン青葉」にもちょくちょく行きます。つい最近も、昼ご飯を求めて神楽坂に出向いたら、神楽坂を少し上って左側の路地を入っていったところで、「和牛小皿しんうち」というお店を見つけました。カウンターのお店でいただくローストビーフ丼は1,000円で、とても美味しかったです。丼のローストビーフの上には卵の黄身が乗っていて、和風サラダも添えてあり、卓上の特製わさびマヨネーズを肉に乗せていただくと絶品です。機会があればぜひ試してみてください。これらのお店以外にも、美味しいお店が多数あるのは、大変恵まれた環境だとつくづく思います。
〈プライベートの森先生〉
さて、締めくくりにプライベートの話を少し。仕事に忙殺される時期は、週末のどちらかは研究室に出向いて作業をしたり、出張で週末がつぶれたりしますが、仕事が忙しくても、なるべく日曜の午前は家族との時間を作って、娘と出掛けたりしています。息子は、高校のバスケ部の活動とオンラインのゲームと予備校で忙しく、もう親離れしてしまいました。週末も練習試合で家を空けることもしばしばです。土曜日は小学校2年生の娘がバレエと水泳の習い事をしているので、車や自転車で送り迎えをしたりしています。土日返上のことも実は少なくないのですが、コロナ前に、余裕がある時などは自宅から車で20分くらいのところに井の頭公園があるので、動物園や水生植物園に行ったり、池でボートに乗ったりしていました。
コロナ前は、TDLやTDSに年に1、2回くらい付き合っていましたが、今年は忙しすぎてパスしてしまいました。妻と娘がコロナ後に開園してから2回くらい行って、抽選制の「美女と野獣」狙いだったようですが、抽選に外れて悔しがっていました。あの抽選制は、乗りたい人に対して結構なリピート効果を発揮しているのではないでしょうか。アトラクションは、どこのテーマパークに行っても、ほぼなんでも大丈夫なのですが、苦手なやつが一つだけあります。それはぐるぐる回るティーカップです。中年ともなると、あれはアトラクションではなく、もはや拷問です(私の中では通称「地獄のティーカップ」)。井の頭動物公園のような一見して平和そうな公園にもヤツが潜んでいるのですが、娘といった時は、なるべくそのエリアに近づかないようにしています。そんなわけで、娘の相手をするのは、なかなか体力を使いますが、気分が癒されて精神もリフレッシュします。
ささやかな気分転換ということでは、コロナ前は出張の飛行機で最新映画を観ていました。もっぱらハリウッド系の映画を観てスカッとします。コロナ禍が起こってからは、海外出張がなくなってしまったのは、機内で映画を観られなくなったので、二重の意味で残念です。去年の年末に運悪くA型インフルエンザにかかってしまった時には、家族を妻の実家に帰して、独りで年越しをしましたが、そのときにそれまで我慢していたNetflixを契約してしまいました。アメリカのドラマは、ヒットするやつはやはり脚本が面白い。ものすごい競争を勝ち抜いて選ばれているからだと思います。最近観たドラマだと、Homelandという、シーズン8くらいまであるCIAの対テロ作戦の女エージェントが主人公のドラマが面白かったですね。そのあとは、まだシーズン1しか出ていませんが、Awayという、火星探査ミッションのクルーたちのヒューマン・ドラマが面白いです。はまると、疲れていても寝る前に一話42分くらい観てしまいます(よく寝落ちもしますが)。
そんなわけで、仕事に追われながら、たまに息抜きをするというのが私の日常です。乱文で失礼しました。
森先生の日常はいかがでしたか?少しでも森先生のお人柄が伝わっていたら嬉しいです!
記事を編集している私(11期生)も先生の多忙さやお話のスケールの大きさに改めて驚かされました!また、多忙な中でもお父さんとして娘さんとの時間を大切にされているところが素敵ですよね!!
11月3日(火)の個別相談会にきてくれると森先生に会えます!
ぜひ森先生、ゼミ生に会いにきてください、お待ちしております!