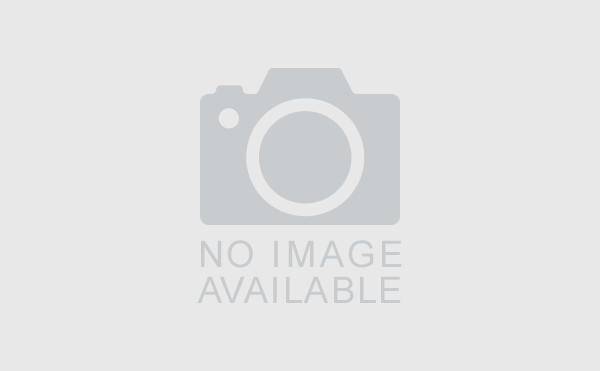7/30のゼミ
(課題)
米ソのデタントを成立させた構造的な条件とは何か?
まずデタントを各班が定義をし、各リサーチプログラムの観点からこの課題を説明した。
主な論点は以下の通りである。
<リアリズム>
大体の班が防御的リアリズムの観点から考察し、米ソ双方にバランスオブパワーの維持に集中した結果、核削減条約の締結に両国が踏み切った。
<リベラリズム>
ソ連の国内事情であった、経済疲弊が経済協調の必要性を発生させた。
課題の議論の中で、「大国と小国の対立、協調は何によって決まるのか?なぜ大国は小国と協調することにインセンティブを見出すのか?」という疑問を森先生からいただき、それぞれが今後考えていくようにと長期的に考えていく課題をもらった。
A班の発表
戦後アメリカ外交史4章
1.冷戦終外交と冷戦後への模索
レーガン政権の登場
国内的-減税と規制緩和
対外的-ソ連を悪の国と非難、軍拡“失われた対ソ優位回復”
悪の帝国の演説(1983年3月)
核軍拡競争の責任が米ソ双方にあるとする核凍結者に強い反論
核凍結に代わる積極的対案として“戦略防衛構想”SDI登場
2.冷戦終結への歩み
米ソ緊張緩和とその背景
83年に米ソ対立がピークに達したことによる関係の行き詰まり
1大統領選挙をめぐる政治的考慮
ゴルバチョフ共産党書記長就任(1985)
レーガン政権期の『人権外交』
友好国に対しても『静かな外交』によって人権侵害への戒め
選挙実施や民主体制への移行を促す
レーガンの遺産
・冷戦終結への筋道
・楽観的なリーダーシップ
3、冷戦の終結
ブッシュ政権の登場
・ソ連各共和国の独立
・東西ドイツ統一問題
4.湾岸戦争と新世界秩序の試練
ブッシュは、国連という多国間協力の場を最大限に活用し、西側同盟国、アラブ諸国、ソ連という利害も思惑も異なる国々の間で困難な協力の枠組みを維持し、湾岸戦争を勝利に導く
“アメリカの目的は、イラク軍のくウェート無条件完全撤退”
*経済制裁から武力行使へ
国連による経済製剤の重要性を強調した
→フセインは経済製剤に動かせず、調停にも応じなかった。
*武力停止の運命
戦闘停止命令について、
フセイン政権を倒する絶好の機会を免
-ブッシュ政権の対外経済政策
1、 対外経済政策
政策の基本は実務的なアプローチによる自由貿易の推進。
2途上国の責務危機にイニシアティーブを発揮
豊田麻希さんの書評
アジア大平洋における地域主義
問題定義
1. 今の東アジア共同体の構造が話し合われている中で、その進展を妨げる要因とは?
2. なぜ中国は独立の危機に直面したときに多国間協調を意識したのか?
遅れてごめんなさい。